裁判所公式「民事訴訟・少額訴訟で使う書式」のうち、「金銭支払(一般)請求」タイプの訴状の書き方。
「記載例」のPDFを見ながら書いて、それで済む場合は問題ないわけだけど、「紛争の要点(請求の原因)」の欄だけでは収まらない場合、少々工夫が必要になる。
まずは、1ページ目から。
事件名
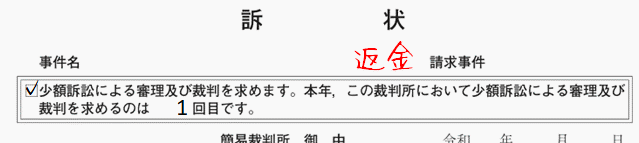
普通は、「返金請求事件」とか「損害賠償請求事件」のように、何の事件だか分からないように書くものらしい(笑)。
もっとも、ボクの場合、何の事件か分かるように「○○○○○返金請求及び損害賠償請求事件」って書いたけど受理されたので、あまり気にしなくてもいいのかもしれない。
チェックマークと●回目
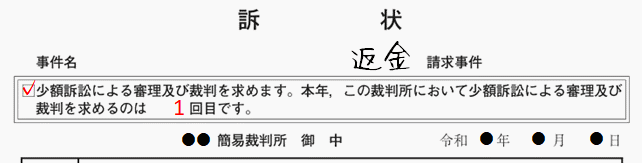
少額訴訟の場合は、チェックマークを入れた上、申し立てる裁判所で今年何回目の利用か(…って普通、1回目だろw)を記入する。
なお、同じ人が同じ簡易裁判所で利用できる少額訴訟は、年10回までらしい(そんな人いるのか?)。
一生に1度も利用しないって人がほとんどだと思うんだけどね…^^;
原告(申立人)
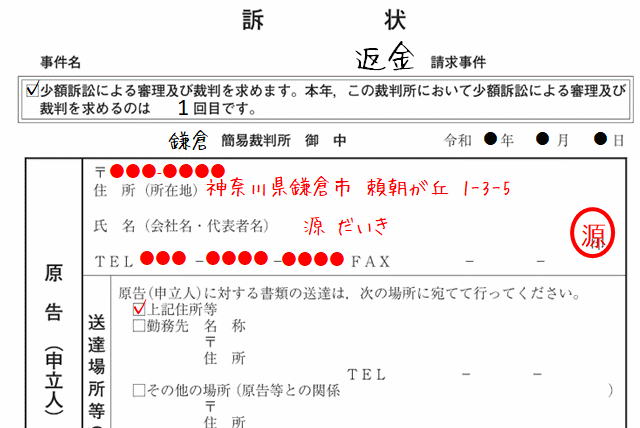
住所、氏名、電話番号は必須。FAXはなくても受理される。
※後に、通常訴訟に移行することになり、月額制のインターネットFAXサービスを利用することになったけどね
「送達場所等の届出」は、「上記住所等」にチェックマークを入れるだけでOK。
被告(相手方)
相手が会社で、詐欺業者みたいなのじゃなければ、被告は1人(=会社)だけで十分だろうけど、相手の会社が吹けば飛ぶような会社だったり、詐欺業者みたいな場合は、被告は会社と代表者個人などの二者にして、連帯債務にしたほうが良いように思う(後述)。
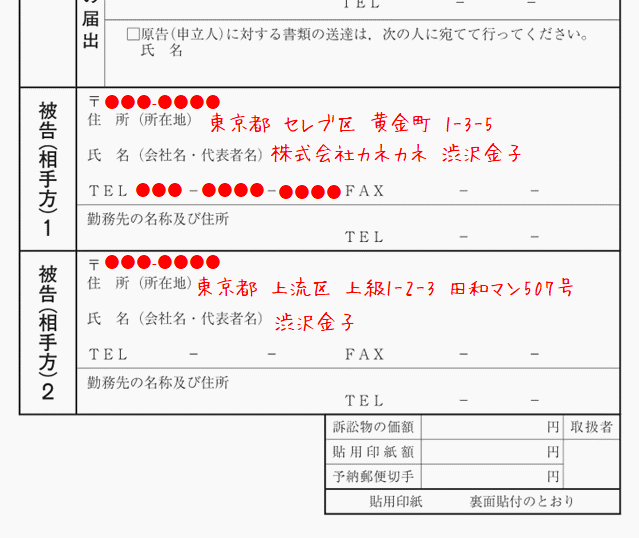
会社の住所も代表者の住所も、会社の登記事項証明書に記載されているので、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を取り寄せてから、それに合わせて記入する。
被告が会社の場合は、登記事項証明書を訴状と一緒に提出する。
2ページ目へ。
請求の趣旨
ここは、ほぼ「金銭支払(一般)請求」記載例PDFと同じでいいんじゃないか?
少額訴訟の訴額の上限は60万円。勿論、60万円満額にする必要はない。
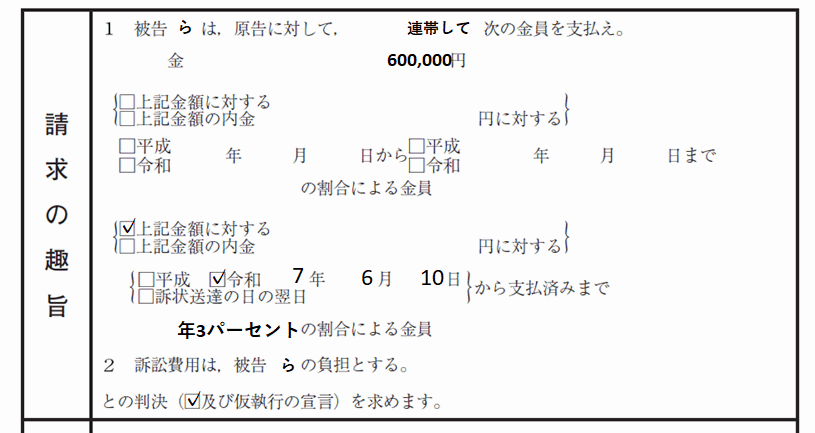
また、利息は年3パーセントにするのがここ最近では一般的だと聞いた。
他に、「{ }から支払い済みまで」のところ、「請求したけど断られたから訴訟を起こす」という場合は、請求した際の「●月●日までに返金されなかったら法的措置を取らせていただきます」の●月●日の翌日から・・・でいいんじゃないかな。
請求した日がつい最近なら、大した違いはないので、「訴状送達の日の翌日」にチェックマークをつけるのもありだと思う(ボクはそうした)。
一番下の「及び仮執行の宣言」にもチェックマークを入れる。
紛争の要点(請求の原因)
ここが、訴状の中核をなす部分で、上記「請求の趣旨」の根拠を示す部分である。
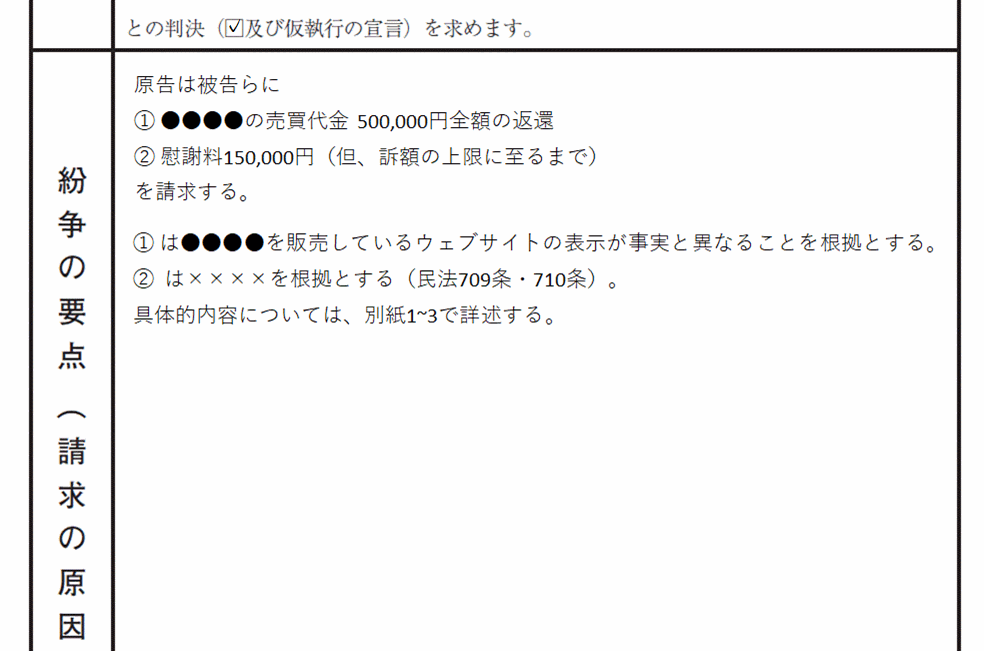
「紛争の要点」とは、争いの核心となる事実のことで、法律用語や条文などを含まない、いわば「フツーの文章」のことで、簡略な内容で良いとされているもの。
一方、「請求の原因」とは、法律用語や条文を含め、法的根拠を示しながら、争点を詳細に記載したもの。
少額訴訟(を含む簡易裁判)の場合、「紛争の要点」で足りるとされているのは、簡易裁判は、一般市民が利用しやすいように手続きが簡略化されているからで、法律用語や複雑な理論構成は求められておらず、争いの「核心」が伝わればそれで十分という考えに基づいている…そうな。
とは言うものの、事前に弁護士に相談して、どのような法的主張ができるかが分かっている場合や、法学部出身者とか司法試験受験経験者のような人なら、遠慮せずに、法的根拠を示しながら主張すればいいんじゃないのかな?
で、今回のボクの訴訟の場合、状況説明を詳細にする必要があって、ダウンロードした訴状のフォームではスペースが足りなかったので、「具体的内容は別紙にて詳述する」みたいに書いて、別紙で詳細を説明するようにした。
※ てか、はじめはそうしないで、適当に端折りながら、狭いスペースに色んなことを書いていたけど、裁判所の人に教えてもらって書き直してから再提出した。
添付書類
会社を相手に訴訟を起こす場合は、会社の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)を自分で取り寄せて提出する。
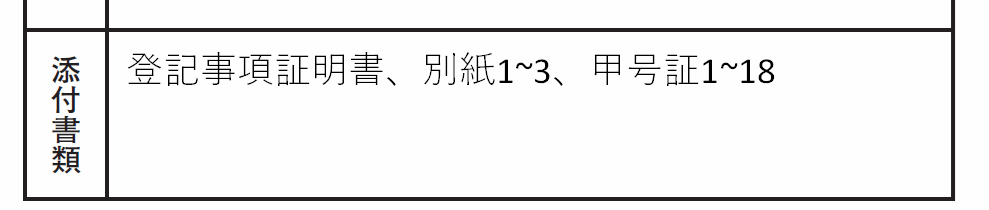
証拠は、「証拠資料1~18」でも受理されたけど、その後、その数字に合わせて「甲第●号証」という番号が振られたので、初めから「甲号証1~18」のほうが裁判所の書記官(進行役の職員)さんに対しては親切だったかもしれない。
証拠が1つ2つくらいしかない場合は、番号を振る必要はないかもしれず、証拠資料そのものについて(「契約書」とか「振込明細」とか)の記述が良いのかも。

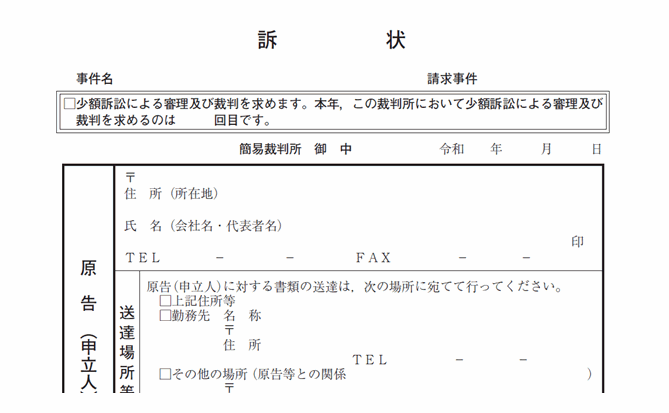
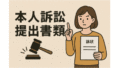

コメント